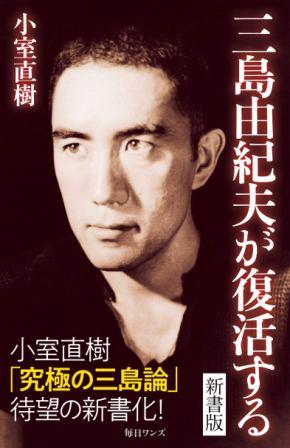
またまた、続き。
意志の力
第三章 復活する三島由紀夫
死霊の世界
「五十になったら、定家を書こうと思います」
三島由紀夫は、友人の坊城俊民氏にそういった(角川書店『焔の幻影ー回想三島由紀夫』坊城俊民)。
二人の会話を、さらに引用しよう。
「そう。俊成が死ぬとき、定家は何とか口実を設けて、俊成のところへ泊らないようにするだろう?あそこは面白かった」(坊城)
「あそこも面白いですが、定家はみずから神になったのですよ。それを書こうと思います。定家はみずから神になったのです」(三島)
神になった定家。それは三島由紀夫にほかならない。
ここで、能の「定家」について書いておこう。時雨の降る初冬が季節になっている。旅僧(ワキ、主役の相手方)が雨やどりしているところへ、式子内親王(シテ、主役)の亡霊があらわれる。
定家と内親王は、人目を忍ぶ仲であった。が、内親王の死後もなお定家の恋する想いはつのり、内親王の墓に定家の執心が、葛となってまといついている。亡霊はそのように訴え、旅僧を自身の墓に導き、回向を依頼する。
式子内親王、はじめは加茂の斎院にそなはり給ひしが、程なく下り居させ給ひしを、定家の卿忍びしのびの御契り浅からず、そののち式子内親王、ほどなく空しくなり給ひしに、定家の執心葛となって、御墓に這いまとひ、互ひの苦しみ離れやらず、ともに邪淫の妄執を、御経を読み弔ひ給はば…定家が、内親王に会ったのは二十歳のとき。一方の内親王は、二十八か二十九歳だったといわれている。
従五位という身分にすぎない定家が、後白河法皇の第三皇女である式子内親王に恋した。忍ばねばならない互いである。
さて、旅僧は内親王の亡霊に依頼されて、読経する。草木までもが成仏するといわれる経文なのである。草木国土、悉皆成仏の秘を得ぬれば、定家葛も、かかる涙も、ほろほろと解けひろこれば、よあしよわぐるまかたくろようと足弱車の、火宅を出でたるありがたさよ。
呪縛からとかれた女は、舞う。だが、その女にはまたもや定家葛が這いまとい、女はそこに埋もれてしまう。
旅僧の読経も、定家の執心を断つことはできなかったのである。
三島由紀夫が書こうとした定家が、この能を下敷きにするものであったのかどうか、もちろん分からない。
だが、三島は、
「定家はみずから神になったのです」
と話している。
これは何を暗示しているのだろうか。
仮面劇の能だが、仮面をつけるのがシテである。シテは、神もしくは亡霊である。
亡霊をシテにして、いわば恋を回想させる夢幻能は、能の理想だといわれる。死から、生をみるのである。時間や空間を超えたものだ。
三島由紀夫が、定家を書こうと考えたとき、やはり能の「定家」が頭にあったにちがいない。
現代では、生の世界と死の世界は、隔絶したものにとらえられている。だが、かつて(中世)は、死者は生の世界にも立ち入っていた。
定家は神になって、生の世界に立ち入ろうとした。そう考えた三島由紀夫ではないだろうか。
生の世界にあっては成就できない事柄を、死の世界に往くことによって可能たらしめようとしたのが、三島由紀夫だった。
第二章で、三島は魂の存在なんぞは認めていないと書いたが、これは決して矛盾していない。ここのところは、よく考えてもらいたい。死の世界で「生きる」三島なのだ。
では、何が目的で三島は死の世界を選んだのだろうか。作品などを引用しながら、自決までの経過は次章に示すが、また、それによって読者も推察可能だろうが、より深い行動の意味は、さらに別にある。
残念だが、いまは具体的には示せない。能の「定家」から賢察してもらうより、方法がない。
あえて死の世界へ往き、守ろうとした存在があったのだ。それは何であったか、どういうものであったか……。
結局この本では語られなかった本当のところ。
なぜミシマは愛欲地獄のストーリーに着目したのか?
死んで神になるとはどゆ事?
ところで、戦前の大日本帝国は、ローマン・カトリックがお手本。天皇中心の共同体。
法律も、「勤労の美徳」など、パウロが創作した戒律がベース。戒律に従わないと「非国民」な、前近代ムラ体制。(これは今もしつこく変わっていない。ゴーン事件で世界から批判される原因)
ローマ教会にイエスは居ないが、大日本帝国は、主権者が「人の子にして神の子」。代替わりしても、今上天皇。不動の、絶対存在。
聖書では一人しかいないはずなのに、なぜか代替わり。
そもそも、イエスはいったい何者か?
記録を辿れば・・・
古代の愛欲地獄
「地球の主」エンキの失われた聖書―惑星ニビルから飛来せし神々の記録 (超知ライブラリー)
ウヌグ・キとアラタを行き来しながら、イナンナは落ち着かず、満たされなかった。
飛び回りながらも、太陽の光にドゥムジが揺らめき招いている姿を見た。
夜には夢に彼が現れ、僕は戻って来るよ、と囁いた。そして、“2 つの峡谷の土地”(エジプト)にある彼の領地の栄光を、彼は約束してくれた。
こんな幻影に、彼女は翻弄されていた。ウヌグ・キの神聖な区域に、彼女はギグヌ、“夜の愉しみの家”を設置した。
そこで、ようやく失われた愛を忘れることができた。
ドゥムジの命日の度に自分の“船”に乗って放浪し、次々と人間の男(王、英雄)を誘い、一夜を共にしたのである。
とりわけ若い英雄たちを、彼らの結婚式の夜に、イナンナは甘い言葉で誘い出した。
花嫁とではなく、彼女と寝ることにより、長生きと至福の未来を約束したのである。
イナンナはドゥムジに思いを馳せながら、彼らと夜を共にした。
そして、“神との遭遇”である“性の儀式”が“聖なる結婚”の儀式としてギグヌで行われるようになった。
夜を共にした男たちの運命は、ある者は翼を破られ、ある者は穴の中に埋められ、またある者は彼女のベッドで死んでいた!このように“聖なる結婚”の儀式は、イナンナにとっても男たちにとっても苦痛を伴う“歓びの命日”だった。しかし、中には生きていた者がいた。
英雄バンダ、ウツの曾孫である。
彼女の住まいでバンダは入浴させられ、房飾りの付いたマントに飾り帯を締めさせられた。
「ドゥムジ、私の最愛の人!」
彼女は彼をそう呼んだ。彼女は花々で飾られたベッドへ彼を誘った。
朝になってもバンダは生きており、イナンナは喜んで叫んだ。
「奇蹟よ、奇蹟だわ!私の最愛のドゥムジが帰ってきたの!」
ウツの恩寵により、彼は死から蘇ったのである。
「死なない力を私は手にした!不死は、私によって授けられたのだわ!」
そして、自分のことを女神イナンナ、“不死の力”と呼ぶことにした。
イナンナの両親は、このような彼女の宣言を喜ばなかった。エンリルとニヌルタは彼女の言葉に狼狽し、ウツは困惑した。
そして、エンキとニンフルサグは
「死者を蘇らせることなど、不可能だ!」
と言った。
幻影が相手では、勝ち目がない。
死ぬ事で絶対者となってしまった、牧神ドゥムジ(タンムーズ)。
人間界に残されたのは、彼の命日に王権を与える、復活の儀式。
話を戻し、ミシマが「敵」と呼んだ偽善者たち。
政府や操り人形である与野党代議士。
もっと辿れば、
操り人形師は、忖度階級制の霞が関サル山。ご本尊は、ジレンマを仕込まれた法体系。そして、その信奉者たち。
巡り巡って、ほふられる者たち。
